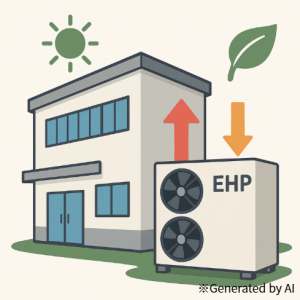
工場の省エネやコスト削減を目的とした設備更新において、熱源の選定は極めて重要な経営判断です。本記事のテーマであるEHP(電気ヒートポンプ)は、電気モーターでコンプレッサーを駆動させる高効率なシステムです。
対比されるGHP(ガスヒートポンプ)には、エンジン特有のメンテナンスコストや振動・騒音、燃料費高騰といった工場ならではの潜在的課題があります。EHPは、そのシンプルな構造によるメンテナンス性の高さやクリーンな稼働でこれらの課題を解決するメリットを持ちます。 導入の懸念(電気代)に対しても、特に徳島(西日本)エリアでは電力の安定性という観点からコストメリットが出やすい側面があります。
本記事では、EHP(電気ヒートポンプ)の概要とGHPとの違いから、GHPが工場で抱える課題、EHPがもたらす省エネメリット、導入懸念(電気代)に対する専門的見地から、徳島脱炭素省エネソリューションが提供する熱源相談まで、詳しく解説いたします。
EHP(電気ヒートポンプ)とは?
EHPとは、「Electric Heat Pump(電気ヒートポンプ)」の略称であり、文字通り電気を動力源として駆動するヒートポンプシステムを指します。工場の空調設備や、生産プロセスにおける加熱・冷却(熱源)として広く採用されています。
省エネルギー性能の高さから近年改めて注目されていますが、まずはEHPの根幹技術である「ヒートポンプ」の基本原理について正確に理解することが重要です。
ヒートポンプの基本原理
ヒートポンプとは、「熱(Heat)」を「汲み上げる(Pump)」技術の総称です。 多くの設備管理者は、「熱」は高温側から低温側へ移動するものと認識されていますが、ヒートポンプはその自然の摂理に逆らい、エネルギー(この場合は電気)を消費して、低温側から高温側へ熱を強制的に移動させます。
この仕組みは、エアコンや冷蔵庫で既にお馴染みのものです。冷媒と呼ばれる物質が、気化(蒸発)する際に周囲から熱を奪い、液化(凝縮)する際に熱を放出する性質を利用しています。
ヒートポンプが「省エネ」である最大の理由は、投入したエネルギー以上の熱エネルギーを得られる点にあります。例えば、電熱線ヒーターは投入した電力(1kW)に対して最大1kWの熱しか生み出せません。 しかしヒートポンプは、空気中や地中・水中といった「熱源」から熱を汲み上げて移動させるため、投入電力(1kW)を「熱を移動させる仕事」に使い、結果として3kWや5kWといった大きな熱エネルギーを取り出すことが可能です。
この効率を示す指標が「COP(Coefficient of Performance:成績係数)」です。 COPが「5」であれば、1のエネルギー投入で5の熱エネルギー(冷熱または温熱)を生み出せることを意味し、この数値が高いほど省エネ性能が高いと評価されます。
EHPの構造と特徴(電気モーター駆動)
EHP(電気ヒートポンプ)は、このヒートポンプのサイクルを駆動させるための動力源として「電気モーター」を使用します。
具体的には、電気モーターでコンプレッサー(圧縮機)を回転させ、冷媒を強制的に循環・圧縮・膨張させることで、熱の移動(冷房・暖房)を実現します。この基本構造は、家庭用のルームエアコンから大規模な工場の業務用空調まで共通しています。
EHPの最大の特徴は、動力源が電気モーターであることに起因します。
- 構造のシンプルさ: 後述するガスエンジン駆動(GHP)と比較し、駆動系にエンジン関連の複雑な部品(点火プラグ、エンジンオイル、冷却水系統など)を必要としません。
- クリーン性: 機器本体(室外機)からは、燃焼に伴う排気ガス(NOxやCO2)が一切排出されません。
- 高い制御性: 電気モーターはインバータ制御との親和性が非常に高く、負荷状況に応じて出力を緻密にコントロールできるため、エネルギー効率の最大化に寄与します。
工場の熱源を選定する上で、この「電気モーター駆動」というEHPの特性が、後のGHP(ガスヒートポンプ)との比較において決定的な差異(メリット・デメリット)を生み出す要因となります。
工場設備としてGHPが抱える潜在的な課題
GHP(ガスヒートポンプ)は、EHP(電気ヒートポンプ)と比較して電力消費(デマンド)を大幅に抑制できるという強力なメリットを持つため、多くの施設で採用されてきました。しかし、そのメリットはGHPの駆動源である「ガスエンジン」に依存しており、工場の設備として中長期的に運用する上では、EHPにはない潜在的な課題(=隠れたコストや管理負荷)が存在します。
特に省エネやコスト削減、作業環境の改善を重視する工場管理者にとって、以下の3つの課題は看過できません。
課題1:定期的なエンジンのメンテナンスコスト(オイル・部品交換)
GHPは「ガスエンジン」を搭載しているため、自動車のエンジンと同様に定期的なメンテナンスが法的に、また性能維持のために不可欠です。
EHPのメンテナンスが主にフィルター清掃や熱交換器の洗浄であるのに対し、GHPはそれらに加えて、
- エンジンオイルの交換
- 点火プラグの交換
- 冷却水(不凍液)の交換・補充
- 各種フィルター類(オイル、エア)の交換 といった、エンジン機構部特有の保守部品交換や点検作業が発生します。
これらのメンテナンスは専門知識を要するため、多くは専門業者との保守契約が必要となり、ランニングコスト(ガス代)とは別枠で固定的なメンテナンス費用が継続的に発生します。設備の老朽化に伴い、エンジンのオーバーホール(分解整備)が必要になれば、突発的に高額な修繕費用が発生するリスクも抱えています。
課題2:工場環境への影響(振動・騒音・排気ガス)
GHPはガスエンジンが稼働するため、EHPの電気モーター駆動と比較して、どうしても「振動」と「騒音」が大きくなる傾向にあります。 工場敷地内の屋外に設置する場合でも、近隣への配慮や、建屋に近い場合は工場内の作業環境(特に静音性が求められる検査室や事務所)へ影響を及ぼす可能性があります。また、振動が躯体(建物の基礎や壁)を伝って、精密機器へ悪影響を与える懸念もゼロではありません。
さらに、ガスエンジンは燃焼を伴うため、必ず「排気ガス(NOx, COxなど)」が発生します。 脱炭素や環境経営(SDGs, ESG)が重視される現代において、敷地内で排気ガスを出すGHPの運用は、環境負荷低減の取り組みにおいてマイナスに働く可能性があります。また、排気(排熱)の方向や場所によっては、作業者の動線や給気口との位置関係にも配慮が必要となり、設置場所の自由度を制約する要因にもなります。
課題3:燃料(ガス)価格高騰のランニングコストへの影響
GHPの主なランニングコストはガス料金です。都市ガスやLPガスは、その多くを海外からの輸入(LNG:液化天然ガスなど)に依存しています。
近年、世界的なエネルギー需要の逼迫や、産油国・産ガス国における地政学リスク(紛争や供給不安)により、これらの燃料価格は高騰し、不安定な状況が続いています。 GHP導入時に「ガス代の安さ」をメリットとして試算していたとしても、将来的に燃料費が上昇すれば、想定していたランニングコストを大幅に超過するリスクを常に抱えることになります。この燃料費の不安定さは、中長期的な設備投資計画や工場運営のコスト管理において、大きな懸念材料となります。
EHPが工場にもたらす3つの「省エネ」メリット
前項で挙げたGHP(ガスヒートポンプ)特有の潜在的課題は、EHP(電気ヒートポンプ)の構造的特徴によって多くが解消されます。EHPがもたらすメリットは、単なるエネルギー効率(COP)の高さだけでなく、工場運営のトータルコスト削減と環境改善に寄与する点にあります。
工場の設備管理者にとって、EHPの導入は以下の3つの具体的な「省エネ」メリット(※ここではエネルギー効率だけでなく、管理工数やコスト削減も含めた広義の省エネとします)をもたらします。
メリット1:構造のシンプルさによるメンテナンスコストの削減
EHPの最大のメリットの一つは、その構造のシンプルさにあります。 EHPの駆動源は「電気モーター」です。ガスエンジンのような複雑な燃焼機関や、それに付随するエンジンオイル循環系、冷却水系、点火系といった機構部品が一切存在しません。
この構造的な違いにより、GHPで必須であった以下のメンテナンス作業が不要となります。
- エンジンオイルの定期交換
- 点火プラグの交換
- 冷却水の管理・交換
EHPの主なメンテナンスは、熱交換器の洗浄やフィルター清掃、冷媒ガスの圧力チェックといった、ヒートポンプサイクル自体の点検が中心となります。これはGHPも共通して行う作業であるため、EHPはGHPのメンテナンスから「エンジン関連の作業・コスト」を純粋に差し引いたものと考えることができます。
結果として、専門業者との保守契約費用を低減できる可能性が高く、突発的なエンジン故障による高額な修繕費発生のリスクも回避できます。これは、工場のランニングコストだけでなく、管理工数(保全計画の策定・業者手配)の削減にも直結する大きなメリットです。
メリット2:クリーンな稼働と設置自由度の高さ(作業環境の改善)
EHPは「電気モーター」駆動であり、稼働中に燃焼プロセスが発生しないため、排気ガス(NOx, COx)が一切発生しません。 これは、脱炭素経営や環境認証(ISO14001など)に取り組む工場にとって、環境負荷(Scope1:直接排出)を低減する上で非常に有効な手段となります。
また、ガスエンジンのような機械的な燃焼・往復運動がないため、稼働音や振動もGHPに比べて格段に小さいのが特徴です。 これにより、工場内の作業環境(騒音規制)や、近隣住民への配慮が必要な場合でも、GHPより柔軟な対応が可能となります。振動が少ないことは、精密機器への影響を懸念するクリーンルームや研究開発棟への併設においても有利に働きます。
排気ガスや騒音・振動の懸念が少なく大きさも小さいため、室外機の設置場所の自由度が高まる点も見逃せません。排気ガスの排出方向や、騒音源からの距離を過度に考慮する必要がなくなり、建屋のレイアウトや空調効率にとって最適な場所に設置しやすくなります。
メリット3:高効率(高COP)化によるエネルギー効率の最適化
近年のEHPは、インバータ技術の飛躍的な進歩により、非常に高いCOP(成績係数)を達成しています。 インバータ制御は、工場の負荷状況(必要な冷熱・温熱の量)に応じて、コンプレッサーを駆動する電気モーターの回転数を緻密にコントロールします。これにより、GHPのガスエンジン駆動(多くは段階的な制御)と比較して、部分負荷時(フルパワーで稼働していない時間帯)のエネルギー効率が極めて高いのが特徴です。
工場運営において、空調や熱源が常に100%の負荷で稼働し続けるケースは稀です。多くの中間期や負荷変動時に、EHPはインバータ制御によって消費電力を最小限に抑え、結果として年間を通したエネルギー消費効率(APF: 通年エネルギー消費効率)を最大化します。
GHPも高効率化が進んでいますが、特に部分負荷時の効率性や制御の応答性においては、電気モーターとインバータ制御の組み合わせに分があると言えます。
EHP導入の懸念点「電気代」について
EHP(電気ヒートポンプ)の導入を検討する工場の設備管理者から、最も多く寄せられる懸念が「電気代の高騰」、特に「電力の基本料金」への影響です。
GHP(ガスヒートポンプ)からEHPへ移行することは、主動力をガスエンジンから電気モーターへ切り替えることを意味します。これにより、工場の総電力使用量(契約電力)が増加し、基本料金が上昇するのではないか、という懸念は当然のものです。 しかし、この懸念は「デマンド」の仕組みと「地域の電力事情」を正確に理解し、対策を講じることで解消、あるいは最小化することが可能です。
「電気の基本料金」への影響はどうか?
高圧電力契約における電気の基本料金は、過去1年間(当月含む)の「最大需要電力」、すなわち「30分間で使用した電力の平均値」の最大値によって決定されます。
確かに、GHPからEHPに更新した場合、空調がフル稼働する夏場や冬場のピーク時に、この最大需要電力が上昇する可能性はあります。 しかし、重要なのは、この需要電力の上昇による基本料金の増加分と、EHP導入によって得られるメリット(GHPのメンテナンスコスト削減、ガス代の削減、高効率運転による従量電料金の削減)をトータルコストで比較検討することです。
また、最新のEHPはインバータ制御によって非常に高効率化されており、負荷状況に応じて出力を緻密に制御します。さらに、工場全体の電力使用を監視するシステムと連携させたり、複数のEHPを段階的に稼働させる(ローテーション制御)といった運用工夫によって、ピーク電力の突出を抑える対策も可能です。 需要電力の上昇上昇を恐れてGHPの課題(高額なメンテナンス費や燃料費高騰リスク)を抱え続けることは、中長期的な視点では合理的とは言えないケースも少なくありません。
なぜ徳島(西日本)エリアではEHPのコストメリットが出やすいのか
EHPのランニングコスト(電気代)は、全国一律ではありません。徳島県を含む「西日本エリア」(四国電力・関西電力・九州電力管内など)は、他のエリアと比較してEHPのコストメリットが出やすいという地理的・経済的特徴があります。また、特に四国地区については関西地区や九州地区と比較して都市ガスが充実していないという特徴があります。
これは、電力の「発電構成」の違いに起因します。 西日本エリアは、(2025年11月現在)原子力発電所の稼働率が比較的安定していることや、再生可能エネルギーの導入が進んでいることにより、火力発電(LNG・石炭)への依存度が相対的に低い傾向にあります。 結果として、電力の「従量料金(使用量に応じた単価)」が、火力発電依存度の高いエリアと比較して安価かつ安定しやすいという大きな利点があります。
EHPの導入は、この安価で安定した電力を最大限に活用する戦略とも言え、徳島エリアの工場にとっては、他地域よりもEHP導入の経済的合理性が高まる要因となります。
地政学リスクを考慮した燃料費(ガス vs 電気)の安定性比較
GHPの燃料であるガス(都市ガス・LPガス)は、その原料の多くを海外からの輸入(LNGなど)に依存しています。 これは、国際的なエネルギー市場の動向や、産油国・産ガス国地域での紛争・政情不安といった「地政学リスク」の影響を極めて受けやすいことを意味します。 (2025年11月現在)依然として続く燃料費の高騰は、まさにこのリスクが顕在化したものであり、工場のランニングコストを直撃し、将来的なコスト予測を困難にしています。
一方、EHPが使用する「電気」は、LNG、石炭、原子力、水力、太陽光など、多様なエネルギー源から生み出されます。特に西日本エリアのように電源が多様化(分散)している場合、特定の燃料(例:LNG)の価格が高騰しても、他の電源である程度カバーできるため、ガス料金ほどの急激な価格変動リスクを回避・分散できます。
したがって、徳島エリアの工場がGHPからEHPへ熱源を転換することは、単なる省S-エネ対策に留まらず、予測困難な燃料費高騰のリスクから工場経営を守るための、中長期的な「リスクヘッジ戦略」として非常に有効であると我々は分析しています。
工場の空調・熱源選定なら「徳島脱炭素省エネソリューション」へ
ここまで、EHP(電気ヒートポンプ)の基本原理から、GHP(ガスヒートポンプ)との具体的な違い、そして工場設備としてEHPが持つ独自のメリット(メンテナンス性、環境性、西日本エリアにおけるコスト安定性)について詳しく解説してまいりました。
EHPとGHPは、どちらかが絶対的に優れているという単純なものではなく、それぞれに明確なメリットとデメリット(特性)が存在します。 重要なのは、GHPが持つ「電力デマンド抑制効果」と、EHPが持つ「メンテナンスコストの低減」「燃料費の安定性(地政学リスクヘッジ)」といったメリットを天秤にかけ、貴社の工場の稼働実態、エネルギー消費構造、そして中長期的な経営戦略(コスト削減、環境経営、設備投資計画)に、どちらが最適であるかを専門的かつ定量的に見極めることです。
特に、徳島県(西日本エリア)の電力事情や、工場特有の環境課題(騒音・振動)を踏まえた熱源選定は、一般的な空調業者の知識だけでは困難な場合があります。
私たち「徳島脱炭素省エネソリューション」は、空調設備単体でのご提案に留まりません。 ボイラーやコンプレッサー、生産設備など、工場全体のエネルギー消費を俯瞰的に診断し、その上で「貴社にとって最適な熱源は何か」を、ライフサイクルコスト(LCC)と環境負荷の両面からご提案することを得意としています。
- 「現在のGHPのメンテナンスコストは本当に適正か?」
- 「EHPに更新した場合の、具体的なデマンド上昇とトータルコストを試算してほしい」
- 「ガスと電気、結局どちらのリスクを取るべきか専門家の意見が聞きたい」
こうした工場の熱源に関するお悩みや、具体的な省エネ診断のご要望がございましたら、まずは当社の「空調機選定に関する熱源相談」サービスまで、お気軽にお問い合わせください。貴社の状況に合わせた最適なソリューションをご提案いたします。
>> 「空調機選定に関する熱源相談」サービスはこちら (https://ohkubo-s.co.jp/business/eco/service/1096/)





