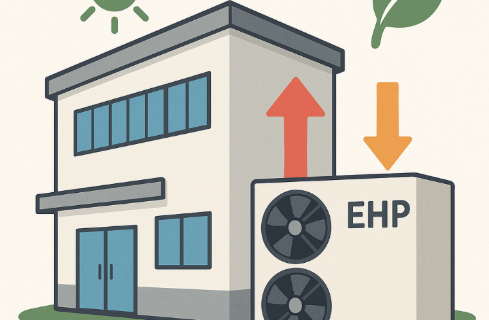製造業における「工場の電化」とは、従来のガスや重油などの化石燃料を使用していた熱源設備や加熱装置を、電気を利用した装置へと置き換えることを指します。これは単なるエネルギー源の変更にとどまらず、エネルギーコストの最適化・BCP(事業継続計画)対策・脱炭素化の推進といった多面的な課題解決策として、いま急速に注目を集めています。
この「電化」は、経済産業省が支援する“燃料転換(燃転)”の一種として分類され、政策的にも国を挙げた導入促進が行われています。特に以下の3つの側面から、工場経営者が今こそ本気で取り組むべきテーマといえるでしょう。
エネルギーコストの安定化と運用効率の向上
工場で使用されるプロパンガスや重油などの燃料は、輸入依存度が高いため、国際情勢の影響で価格が変動しやすい特徴があります。特にプロパンガスは、都市ガスに比べて2〜3倍の単価となるケースもあり、コスト負担が重くのしかかります。
一方、電気は単価の変動幅が比較的安定しており、電化によってエネルギーコストの平準化が可能になります。また、電気加熱装置はオンオフ制御や温度調整がしやすく、熱効率の向上や省エネ運転のしやすさも大きなメリットです。
災害時復旧・BCP対応力の向上
災害や事故の際、ライフラインの復旧速度は「電気 > 水道 > ガス」の順であることが統計的に示されています。特にプロパンガスは個別配管で供給されているため、復旧までに時間を要しやすいインフラです。
電化により設備を電気系統に一本化すれば、復旧のスピードを早め、BCP対策としても有効です。さらに、太陽光発電や蓄電池との連携も可能になるため、災害時の稼働継続や一部ライン稼働の確保が現実的になります。
脱炭素社会への対応と企業価値の向上
2050年カーボンニュートラル実現を掲げる日本政府の方針に従い、企業にも温室効果ガスの削減が求められています。工場の電化は、化石燃料の直接燃焼を避けられるため、CO₂排出量を抑制する具体的な手段となります。
加えて、再生可能エネルギーとの連携によって「ゼロエミッション体制」を構築することも可能です。こうした取り組みは、投資家や取引先からの評価を高めるESG(環境・社会・ガバナンス)経営の一環としても有効に働きます。
補助金制度による導入コストの軽減
電化には設備更新やインフラ整備が必要なため、初期投資がネックとなりがちです。しかし、国の支援制度(例:SII「電化・脱炭素燃転支援」補助金)を活用することで、導入費用の3分の1〜2分の1が補助されるケースもあります。
導入時の調査・計画立案から、補助金申請・施工・運用までを一括支援する専門業者に依頼すれば、負担なくスムーズに電化移行が可能です。
工場の電化は、単なるエネルギー変換ではありません。それは、持続可能な経営と社会的責任を同時に実現する戦略的投資であり、将来を見据えた工場経営において極めて重要な選択肢といえます。
電化によるエネルギーコスト削減
工場運営におけるエネルギーコストは、製品原価に直接的な影響を及ぼす重要な要素です。特に近年、原油価格の高騰や燃料輸送コストの上昇により、ガス・重油などの化石燃料依存による負担が深刻化しています。そのような状況において、工場の電化はエネルギーコスト削減の有効な施策として、再注目されています。
電化は単に「エネルギー源を電気に切り替える」だけでなく、コストの安定化、制御性の向上、熱効率の改善という三つの視点から、運用面での優位性を発揮します。
電気 vs プロパンガス:単価比較と価格安定性
プロパンガス(LPG)は、地域によって価格差が大きく、1㎥あたり400〜700円前後という高単価なケースも珍しくありません。一方、電力は契約プランや使用時間帯により料金は変動するものの、相対的に価格の透明性と安定性が高い点が特徴です。
また、プロパンガスはボンベ配送が中心であり、輸送コストや保管スペース、点検管理コストも間接的にコストアップの要因となります。
電気加熱設備の高効率化と制御性
電気ヒーターや誘導加熱(IH)、赤外線加熱装置など、近年の電化設備は熱効率90%以上を実現しており、従来の燃焼式機器に比べて非常に効率的です。加えて、温度制御やON/OFF制御の自由度が高く、無駄な待機加熱を避けることで消費電力量を抑制できます。
たとえば、精密部品の熱処理や乾燥工程においては、電気による加熱が時間・温度の均一性に優れており、品質の安定にも貢献します。
省エネ補助金との併用で導入コストを吸収
電化設備は、初期投資が高額になりやすい傾向がありますが、国や自治体の省エネ補助金制度を活用することで、実質的なコスト負担を大幅に削減できます。特に「電化・脱炭素燃転支援補助金」は、導入費用の1/2を補助する制度もあり、条件が合えば導入リスクを抑えながら本格的な電化が可能になります。
さらに、エネルギー使用量の見える化(EMS導入)や自動制御システムとの組み合わせにより、運用段階でも着実な省エネ効果が期待できます。
このように、電化は単に“ガスから電気に変える”だけでなく、長期的なコスト最適化・生産性向上・品質安定にまで波及する経営戦略の一手となります。特に燃料コストが経営を圧迫している企業こそ、電化による構造的な見直しが求められる時期に来ているといえるでしょう。
災害・停電時のBCP対策としての工場の電化
自然災害や事故発生時、工場の稼働継続に大きな影響を与えるのが「ライフラインの復旧スピード」です。生産ラインの停止は、顧客納期の遅延、品質低下、売上損失に直結するため、BCP(事業継続計画)対策は企業の信頼性を左右する要素ともいえます。
その中でも、工場設備の電化は、災害リスクに強い工場をつくるための実効性ある施策として注目されています。
ライフラインの復旧速度:電気>水道>ガス
気象庁や経済産業省などの公的データによれば、災害発生後のインフラ復旧速度は「電気」が最も早く、多くの地域で災害発生から1~3日以内に通電が回復しています。一方、水道は配管破損などにより時間がかかる傾向があり、「ガス」は特に復旧までに1週間以上かかる例も珍しくありません。
プロパンガスにいたっては、各工場が個別にボンベ供給を受けているため、地域インフラではなく“自助努力による復旧”が求められるインフラです。電化により主要設備を電気系統へ切り替えることで、こうした復旧格差の影響を最小化することができます。
災害時でも稼働可能な「自己完結型エネルギーシステム」へ
電化のもう一つの大きな利点は、太陽光発電や蓄電池との親和性が高いことです。再生可能エネルギー設備や非常用電源と連携することで、「停電時にも最低限のラインが稼働できる工場」へのアップグレードが可能になります。
たとえば、照明、換気、品質管理システムなど、最低限のインフラを電気で確保できれば、工場全体の停止を防ぐだけでなく、顧客との信頼維持や製品の緊急供給にも対応できます。
BCPの観点から見た電化の優位性
多くの中小企業では、BCP対策としての自家発電機やガス備蓄を進めていますが、日常的に使われない非常用設備は老朽化・維持管理コストの課題があります。
一方、電化は「通常時の効率向上」と「非常時の継続稼働」を同時に満たすことができ、BCPと経営効率化を同時に実現できるアプローチとして合理的です。さらに、電化対応の補助金制度も利用可能なため、BCP対策としての投資回収性も高く評価されています。
BCPの要となるのは、「万が一のときに、何を優先して動かすべきか」をあらかじめ決め、そのためのインフラを日常的に運用しておくことです。電化は、平常時の省エネ+非常時の稼働継続=両立可能な体制づくりに繋がる、次世代型のBCP対策なのです。
電化はなぜ環境に優しい?脱炭素と電源のクリーン化
脱炭素社会の実現に向けて、日本の産業界は大きな転換期を迎えています。特に製造業においては、工場のCO₂排出量削減が喫緊の課題であり、その有効な対策の一つとして「電化(燃料転換)」が挙げられます。
従来のボイラーや加熱装置では、プロパンガスや重油の燃焼により大量の二酸化炭素が発生しますが、これらを電力ベースの設備に置き換えることで、CO₂排出の大幅な削減が可能になります。
電化によるCO₂直接排出の削減
化石燃料を直接燃やす工程では、その場で大量のCO₂が排出されます。一方、電化された設備では、設備自体からのCO₂排出はゼロです。もちろん、電力の供給元が火力発電であれば間接的な排出は避けられませんが、全体としての排出削減効果は非常に高いとされています。
また、近年は電力会社各社が再生可能エネルギーの比率を高めており、「再エネ由来の電力」へ契約を切り替えることで、間接排出(スコープ2)の削減も現実的になっています。
電化は「再エネ活用の下地づくり」にもなる
再生可能エネルギー(太陽光・風力など)と工場設備を連携させるには、エネルギーの“電化”が前提条件となります。プロパンや重油では、再エネの電力を直接活かすことはできません。
工場設備を電化しておけば、将来的に太陽光発電や蓄電池との接続もスムーズになり、自己消費型のエネルギー循環(自家消費+売電)の実現にもつながります。これは、脱炭素に向けた第一歩であると同時に、エネルギー自立性の強化にも貢献します。
ESG・カーボンニュートラル経営に応える施策
脱炭素は、環境対応というよりも「企業価値の根幹」に関わるテーマへと進化しています。特に大手メーカーとの取引や、海外展開を視野に入れた企業では、「スコープ1・2排出量の把握と削減」がサプライチェーン全体で求められます。
工場の電化は、スコープ1(直接排出)を明確に削減できる即効性のある施策であり、ESG・SDGs・カーボンニュートラルといった世界的な潮流に対応する手段として高く評価されます。
今後の展望と企業の責任
政府は2030年までに温室効果ガスを46%削減(2013年度比)という目標を掲げており、産業部門にも大幅なCO₂削減が求められています。こうした中で、電化は“いますぐ着手できる”脱炭素策のひとつであり、対応の遅れは企業評価の低下や調達制限につながりかねません。
だからこそ、技術的にも実現可能で、かつ補助金活用によりコスト面も抑えられる電化の導入は、経営的にも理にかなった選択と言えるのです。
工場の電化は、単に環境に「優しい」だけでなく、企業が次の10年を生き抜くための競争力の源泉です。環境対応は、もう“プラスアルファ”ではなく、標準装備といえる時代が到来しています。
大久保産業ならではの工場の電化
工場の電化は、省エネ・災害対策・脱炭素といった多面的な課題解決につながる一方で、設備の選定や補助金申請、現場施工には高度な知見と実務力が求められます。単なる設備販売業者や設計会社では、こうした領域を網羅することは難しく、“どこに相談するか”が成果を左右する重要なポイントです。
当社は、長年の実績と専門的な許可体制、そして最新技術を取り入れる独自のネットワークによって、他にはない強みを活かした総合的な電化提案を行っています。
創業90年超・累計数万件の工事実績
当社は創業から90年以上、地域密着で設備施工・メンテナンスを手がけてまいりました。工場の省エネ、IoT化、環境改善に関する案件を年間300件以上実施しており、あらゆる工場設備・エネルギー課題に対して最適な提案と確実な施工が可能です。
現場ごとの事情や過去のトラブル事例を踏まえた対応ができる点は、経験に裏打ちされた企業ならではの強みといえます。
建設業許可11種+県指定“特A”業者の安心感
当社は電気工事にとどまらず、土木・建築・配管・機械器具設置など合計11種の建設業許可を保有しています。これは工場設備に必要なすべての分野を、社内で一貫して対応できる体制が整っていることを意味します。
さらに、公共工事において県から“特A”指定を受けており、安全性・品質・納期管理において公的にも高い信頼を得ています。
工場電化を検討されている方へ|まずはお気軽にご相談ください
工場の電化は、単なる省エネ対策にとどまらず、エネルギーコストの安定化、BCP(事業継続計画)対応、そして脱炭素経営の推進といった多方面の経営課題に対して、有効なソリューションとなります。
しかし、「具体的にどこから着手すればよいかわからない」「補助金の手続きが複雑そう」「自社の設備で本当に効果が出るのか不安」という声も少なくありません。
当社では、以下のようなサポートを一貫して提供しています
- 現地調査・エネルギー使用量の診断
- 設備更新・電化プランの設計提案
- 補助金(SII等)の申請サポート・実務代行
- 電気工事・施工管理・アフターメンテナンス
- 再エネ連携や省エネ技術の継続提案
- 毎月の情報誌による最新事例・技術の提供
特に補助金制度の活用は、タイミングと制度理解が重要です。弊社では、制度の公募情報をいち早くキャッチし、お客様に最適なプランをご提案する体制を整えています。
また、当社の強みは“営業だけ”ではなく、創業90年以上の現場力・設計力・施工力を活かし、技術的な根拠に基づいた電化提案を一貫して実現できる点にあります。
ご相談・お問い合わせについて
- 「まずは話を聞いてみたい」
- 「省エネ・電化の可能性を知りたい」
- 「どの補助金が活用できるかだけ教えてほしい」
このような内容でも構いません。お電話またはフォームより、お気軽にお問い合わせください。